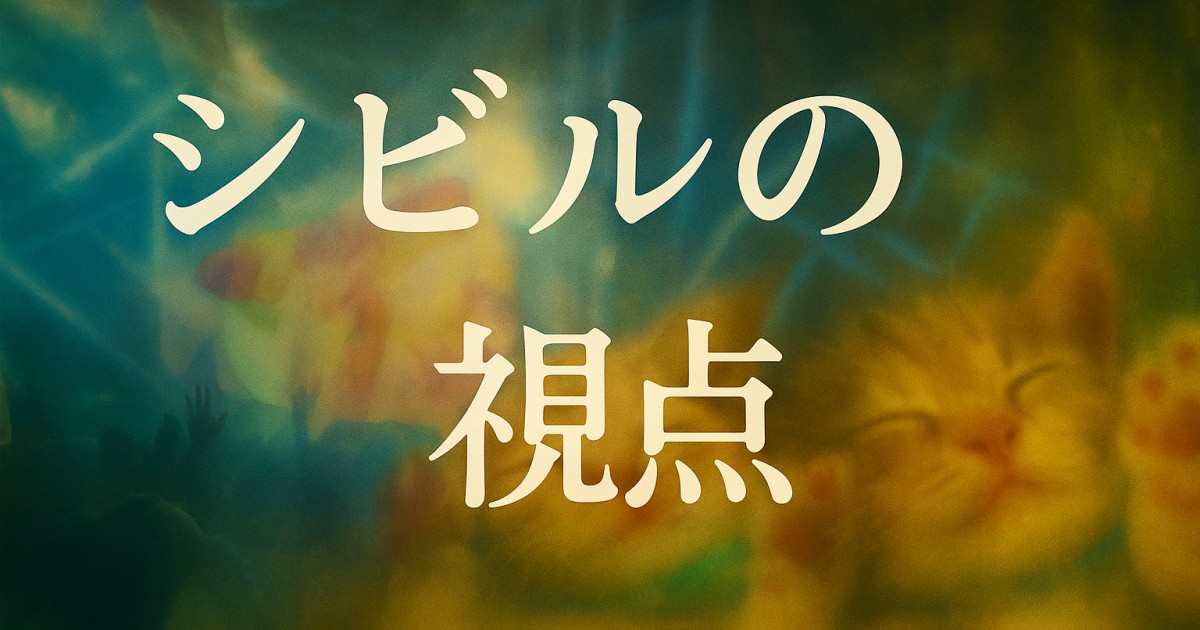出版業界の歴史(1)雑誌と書籍
1.近代の夜明け
現在の出版業界の成立は近代社会の成立と発展とに対応しています。
近代技術というのは、人力から自然エネルギーを利用した生産の効率化による大量生産の技術です。さまざまな機械や製品が大量生産されてきました。モックアップ(モック)と呼ばれる原型を人間が作り、それを型にして同じものを大量に生産する技術です。最近ではモックそのものも機械が作るようになりました。つまり近代とはコピペ文化なのです。
出版産業の土台にあるのは近代印刷技術の発展とともにあります。明治時代には活版印刷が日本に導入され、大量生産の新聞や書籍の印刷製造が可能になりました。新聞が販売されるためには記事が必要であり、やがて新聞による連載小説が人気になり、その連載を書籍化してベストセラーが誕生します。
明治時代に「食道楽」(くいどうらく)という村井弦斎のグルメ本が大ベストセラーになりました、もともとは報知新聞で連載したものを書籍化したものです。報知新聞は当時の大新聞社の一つで、やがて読売新聞に吸収合併されました。
「食道楽」は日本のグルメ本の元祖であり、メディアが時代を作った初期の現象として重要な人物である。この本で村井弦斎は巨額の印税を獲得し、家には専門のコックを雇ったと言われている。ある日、取引先の銀行の店長が自宅を訪問し、なんのことかと思ったら、自分の息子を作家にしたいのだが、どうすればよいかと指南を仰ぎにきた。新聞社や出版社から送金されてくる金額が相当なものなので、銀行の店長は自分の息子を作家にしたいと思ったようだ。
なお「食道楽」は、亀田武嗣が現代語訳にして出版しました。
2.雑誌と書籍
「食道楽」はやがて雑誌にもなりました。「新聞」「雑誌」で連載して、書籍というパッケージにまとめるという手法は、近代の開始から起きていたことです。
現代の大手出版社には「雑誌部」と「書籍部」があります。だいたい仲が悪い(笑)。それは「雑誌」と「書籍」は同じ近代技術を使った大量生産システムですが、雑誌は「今」を大事にして、最新の情報や人々が知りたいことを読者の代理人として取材し調査してニュースや評論として掲載します。それは政治、ビジネス、カルチャー、金融、医療、スポーツ、芸能、旅行、関心のある読者層があれば、その関心の代理人として取材して原稿化します。
雑誌は最新情報を提供することの使命感があるので、ある意味、荒い。確たる証拠が揃っていなくても、記事にして走ってしまうこともある。しかし、そのことによって闇に隠されていた巨悪が白日の陽にさらされたこともたくさんあります。大事なことは、時代の動きと同伴しながら走る疾走感です。雑誌記者は次から次に新しいネタやテーマや人の関心に向かいます。
それに対して書籍というのは、もうすこし長期的な視点を持ちます。制作過程も、本来は著者との対応で何年もかかることはよくあります。雑誌がスピード感やライブ感を大事にするのに対して、書籍は今の時代を越えて長期的で普遍的な価値を求めます。私たちは明治の夏目漱石の本を通して、近代を迎えた日本人の不安な心性を受け取ることが出来ます。
同じ紙の印刷物を作っていても「雑誌」と「書籍」では方法論が違いますから、そりゃあ、対立します。
さて現在、出版界は不況産業と呼ばれています。構造不況とも。しかし、私がみる限り、不況なのは「雑誌」だと思います。それと「雑誌のように作られた書籍」です。本来の時間をかけて歴史に残すために作られた書籍は、もともと小さなマーケットであり、50年前も現在もあまり変わっていないように思えます。
80年代バブル以後、雑誌はバブル経済の巨大な広告の受け皿とし爆発し、その広告収入で人件費を高騰させました。それまでの書籍というのは著者が人生を賭けてゆっくり書いていたものが、バブルのスピードに合わせて、トレンディドラマよろしく、タレント集めたり雑誌的な最新話題追求型になったり、コピペ型の大量生産著者が生まれ、編集プロダクション制作の「書籍」が溢れたのです。
しかし、そうした雑誌の方法論はすべてインターネットに吸収されました。最新ニュースも、スターの写真も、業界のトピックスも、あらゆる領域の「ここだけの話」がインターネットで公開されています。当然、雑誌広告の価値も失っていきました。
こうした状況の中で「シェア書店」が生まれてきた意味を、もういちど、出版業界の人は考えた方がよいと思います。
(続く)
すでに登録済みの方は こちら